無垢材
- 特徴
- 色・デザイン
無垢材とは?集成材との違いとそれぞれのメリットについて
2021.03.24
無垢材とは、どういうものかご存知ですか?木材そのままのこと?集成材の対義語?
「無垢材」と「集成材」の違いやメリット、デメリットをそれぞれ明確にお伝えします。
どちらも理解した上で木材選びを検討してみてください!
それではいきましょう〜
無垢ってどういう意味?
そもそも「無垢」という言葉ってあまり馴染みがないですよね。直訳すると「垢(あか)がないこと」ですが、もともとは仏教用語で「煩悩のけがれがなく,清らかなこと」「けがれがなく純真なこと」という意味があります。一般的には「白無垢」「純真無垢」といった言葉によく使われますね。
無垢材とは、この「無垢」という言葉を使った木材、ということになります。
無垢材とは?
では、無垢材とはどんなものなのでしょうか?
「無垢材とは」と調べてみると以下のような説明がありました。
https://www.homepro.jp/
https://www.maff.go.jp/
https://www.kodansha.co.jp/
参考:コトバンク
https://kotobank.jp/
つまり、、、
無垢材とは、丸太から直接必要な寸法で切り出した木材のことで、割れやひびなどが入りやすいが、天然木本来の風合いや特性を持っているのが特徴です。

集成材とは?
無垢材についてよくわかったので、次に、一般的に使われる「集成材とは」と調べてみると以下のような説明がありました。
https://www.homepro.jp/
https://www.maff.go.jp/
https://www.kodansha.co.jp/
参考:コトバンク
https://kotobank.jp/
つまり、、、
集合材とは、薄く切り出した複数の板を接着剤で貼り合わせた建材のことで、任意の大きさや形をつくることができ、割れや狂いが生じにくいのが特徴です。
無垢材のメリット
無垢材とは、丸太から切り出したままの木材のことで、木材本来の特性を持つことがわかりました!それでは、無垢材のメリットはどのようなものなのでしょうか?具体的に詳しく見ていきましょう!
経年変化を堪能できる
無垢材の最大のメリットとも言えるのが「経年変化」です。経年変化とは、文字通り「時の経過とともに変化する」ことで、時の経過とともに変化する無垢材の表情を楽しむことができるのです。無垢材の色が淡色から赤褐色に変化したり、マットな質感から徐々にツヤがでてきたりと、種類によってさまざまな変化があり、味わい深くなっていきます。
調湿作用で年中快適に過ごせる
無垢材には、調湿作用があります。調湿作用とは、空気中の湿度を調整する作用のことです。空気が乾燥する冬場などは、無垢材に含まれる水分を空気中に発散し、じめじめする夏場には、空気中の水分を吸収したりするとこで調湿します。過乾燥やじめっとした空気を変え、空気中の湿度を一定に保とうとする作用があるのです。これにより、梅雨や夏季の湿度が高い時期でも無垢材はサラッと快適に過ごすことができます。
身体に優しい
無垢材は、接着剤をほとんど使用しません。接着剤はシックホーム症候群などを引き起こすとされている有害物質、ホルムアルデヒドを含むと言われています。接着剤の劣化や夏の暑い時期に接着剤が気化すると空気中に有害物質を発生させる可能性があるそうです。無垢材にはその接着剤をほとんど使用しないため、身体に優しいのです。

木材本来のあたたかみがある
無垢材は天然木100%のため、木材本来の特徴を色濃く残しています。建材として使用する場合、十分に乾燥させますが無垢材には多くの空気が含まれます。この空気が熱伝導率を下げてくれます。木材って鉄などと比べると圧倒的に熱伝導率が低いんです。フライパンの鉄部分はあつあつでも木の取手部分は熱くならないですよね。あれは木材と鉄の熱伝導率の差を利用してるんです。そんなわけで木材は熱伝導率が低くなります。無垢材をフローリングに使うと冬場のひやっとした感覚がありません。冬場でもほんのりあたたかい無垢材を堪能することができます。
木材の生命力を感じられる
無垢材の持つ木目は1つとして同じものは存在しません。種類や切り出し方によって木目の見え方は変わり、はっきりしたもの、繊細なもの、さまざまです。木材の生命力と重厚感を感じられますね。
リラックス効果がある
無垢材は、木材本来の香りも残しています。スギやヒノキなどの針葉樹はメープルやチェストナットなどの広葉樹に比べて香りが強いのが特徴です。木材の香りにはリラックス効果や睡眠の質も向上するというデータがあります。無垢材は見た目だけでなく、人体のリラックス効果をもたらします。
無垢材のデメリット
たくさんある無垢材のメリットですが、木材本来の特徴からくるデメリットもあります。こちらも詳しく見てみましょう!
水分に弱い
無垢材は、表面を加工しても、水分に弱いという特徴があります。そのため、水に濡れたらすぐに乾いた布巾で拭き取る必要があります。また、無垢フローリングを濡れたまま放置しておくとカビや菌の繁殖の原因となります。こまめな拭き取りを心がけましょう!
膨張・縮小を繰り返す
無垢材の持つ調湿作用によって、無垢材は膨張と縮小を繰り返します。乾燥する冬場には無垢材の含む水分を発散するので縮小し、湿度の高い梅雨や夏場には空気中の水分を吸収するので膨張します。フローリングに無垢材を使用している場合、縮小すると隙間が大きくなったり、膨張すると隙間のゴミを取り出しにくくなったりします。また、膨張や縮小を繰り返す中でソリや割れが発生することもあります。ただし、この収縮は施工前に抑えることができます。木材の含水率が18%以下になると変形を起こしにくくなるので、施工前に業者と相談することをおすすめします。
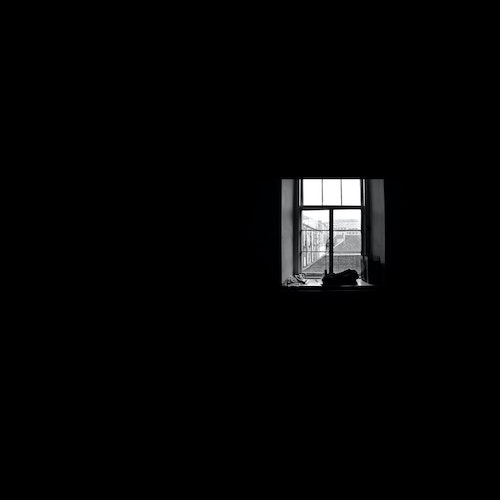
傷がつきやすい
無垢材は、集成材と比べると傷がつきやすいという特徴もあります。無垢材の種類やグレードにもよりますが、スギやヒノキなどの針葉樹は柔らかいため硬いものを落としただけでも傷がつくことがあります。メープルやチェストナットなどの広葉樹は比較的硬く、傷がつきにくい木材です。
価格が高い
無垢材は、種類やグレード、生産量や出荷量にもよりますが、集成材に比べると価格が高い傾向にあります。高級木材としてはケヤキが日本人には馴染みがありますよね。一般的に針葉樹より広葉樹の方が価格設定が高くなります。
集成材のメリット
木材本来の味わいを堪能できる無垢材に対して、集成材ならではのメリットもあります。
品質が安定している
人工的につくられた集成材は割れや狂いが発生しない点が最大のメリットとも言えるでしょう。乾燥した薄い合板を使っているので、品質が安定するのです。また、無垢材は出荷量や生産量によって価格が変動したり、強度が異なったりすることがあります。その点、集成材は安定した供給量を担保できるので、価格も品質も安定して居ます。

デザインが豊富
集成材は人工的に作成されるため、デザインの種類が豊富です。また、木材によって木目や形にばらつきのある無垢材に対して、集成材は色やデザインも統一することができます。一風変わったデザインやおしゃれな木目も実現することができます。最近では見た目上無垢材と遜色ないデザインもあるのでチョイスの幅が広がるでしょう。
強度が高い
傷や水分に強いのも集成材のメリットです。無垢材は種類やグレードによって傷つきやすさが変わりますが、集成材の強度は建築基準法で決まっているので、バラつきがありません。地震や台風などの災害が多い地域では特に嬉しいメリットですよね。
価格が安い
集成材は無垢材と比べると価格が安いです。大量生産で安定した品質と生産量を担保できることが要因です。
集成材のデメリット
耐用年数が短い
集成材の耐用年数は10〜15年と言われていて、これは、集成材に使われる接着剤の寿命と関係しています。一方、無垢材の耐用年数は30〜50年、長ければ80年以上とも言われています。導入コストは無垢材の方が高価ですが、長い目で見ると無垢材の方が経済的とも言えるかもしれません。
木材本来の特徴はない
集成材は無垢材の特徴をなくし、扱いやすくしたものです。つまり、夏場の湿度を吸収したり、断熱性はありません。そのため、湿度の高い夏場はじめっと、冬場はひやっとした肌触りになります。また、唯一無二の木目も存在せず、均等なデザインとなります。

経年劣化が発生する
「経年変化」のおこる無垢材に比べて、集成材には「経年劣化」が発生します。つまり、時の経過とともに品質が劣化していくということです。新品状態が1番美しく、10〜15年で劣化し張り替えや取り替えのタイミングとなります。
無垢材と集成材の特徴やメリット、デメリット【まとめ】
いかがでしたか?無垢材と集成材の違いや特徴、それぞれのメリットについてまとめました。木材ならではのメリットと、大量生産ならではのメリットがありましたね。
どちらもメリットがあるので迷いどころですが、私的には、木材本来の味わいを堪能できる無垢材がやっぱり気になるところです。
まあ、費用とも相談が必要ですが、、、汗
本日はここまで!
ありがとうございました〜!
Category カテゴリー
その他の無垢材
-
無垢材
無垢材ってなに?無垢材の特徴とメリットデメリットをご紹介!
- 特徴
- 傷
- 色・デザイン
-
無垢材
無垢材にカビが生えてしまったら?原因と対処法をご紹介!
- リハビリ施設
- 傷
- 手入れ
-
無垢材
無垢材のへこみの補修方法をご紹介!すぐにへこみ傷を修復しよう!
- 傷
- 手入れ
- 補修
1分簡単入力で
