無垢材
- リハビリ施設
- 傷
- 手入れ
無垢材にカビが生えてしまったら?原因と対処法をご紹介!
2021.03.10
無垢材にカビが生えってしまったことはありませんか?そんなときは諦めずにすばやく対処してみましょう。今回は無垢材にカビが生えてしまったときの対応方とその予防方法をお伝えします!
無垢材のことをよく知って、上手に付き合っていきましょう〜!それではまいります!
無垢材とは?
そもそも、「無垢材」とは、どういうものかご存知ですか?
あまり馴染みのない方も多いのではないでしょうか?
「無垢材」とは、一言で表すと「木材そのまま」といったところでしょうか。つまり、丸太から必要サイズに切り出した一枚板をそのまま加工したものです。木材本来の特徴を色濃く残しているため、木材の持つあたたかみや重厚感、リラックス効果などが期待できます。また、シックハウス症候群を引き起こすとされる接着剤をほとんど使用しないため、身体に優しいというメリットも持っています。さらに、時の経過とともに表情を変える「経年変化」を楽しめるのも無垢材の特徴といえます。
一方、一般的に使われる「複合材」は複数の薄い板(合板)を接着剤を使って貼り合わせています。大量生産により、品質の安定性が担保され、デザインの豊富さや価格を抑えられることがメリットです。ただ、合板を貼り合わせているため、木材本来の特徴であるあたたかみや調湿作用などはほとんどありません。
ちなみに私は最初、無垢材とは木材であることすら知りませんでした、、、

無垢材の特徴
木材本来のあたたかみが残っている
無垢材は天然木100%なので、木材が本来持っているあたたかみを色濃く残します。木材は水分をふんだんに含んでいるため、この水分が断熱効果を持ちます。これにより、冬場の無垢フローリングの上を素足で歩いても、ほんのりあたたかみを感じることができるのです。また、無垢材の木目は1つとして同じものは存在しないので、
リラックス効果がある
無垢材はいわば木材そのままなので、木材本来の香りを持っています。無垢材の種類にもよりますが、ほのかな木の香りは心身ともにリラックスさせてくれることが科学的に証明されています。人間は、木の香りをかぐと血圧が下がることからリラックスでき、さらにそのリラックス効果により精神的な発汗などが抑えられ、睡眠の質も上がると言われているのです。木の香りに包まれた暮らしはリラックス効果をもたらし、仕事の効率もあげてくれるということです。スギやヒノキなどの針葉樹の方が香りが強く、ナラやメープルなどの広葉樹は香りが弱い傾向にあります。
経年変化を楽しめる
無垢材の最大の特徴ともいえるのが「経年変化」です。時の経過とともに無垢材の見せる表情が変わります。変化の仕方は木材によりますが、淡色から赤褐色、ツヤ目からマットへといったように色や風合いが変化していきます。真新しい無垢材と5年、10年経過した無垢材では、見せる表情が全く違うというわけです。少しずつ変化していく無垢材とともに、家族の成長を感じられると、とても味わい深いですよね。
水分に弱い
無垢材は水分を含むと膨張するという特徴があります。反対に、乾燥すると縮小します、詳しくはこれから説明しますが、この膨張・縮小を繰り返す性質が原因で無垢材にソリや割れが発生することがあるのです。そのため、水分をこぼしてしまったらすばやく乾いた布巾で拭き取る、または無垢材を使用する際に特殊加工をほどこすことにより水分への耐性をつけることもできます。

無垢材にカビは生えにくい?
無垢材は調湿作用を持つので、カビはもちろんダニも発生しにくいと言われています。
調湿作用とは、木材がもつ作用のことで、水分を空気中に発散したり、空気中の水分を吸収して室内の湿度を一定に保とうとする作用のこと。
つまり、無垢材が湿度の調整機能を持っている、ということです。
さらに、木材には多く空気が含まれており、この空気が断熱機能として働き、熱伝導率を下げます。フライパンなど、鉄部分は熱されていても取手の木材部分は常温を保たれているのは鉄と木材の熱伝導率が大きく違うためなんですよ。つまり!無垢材は空気による断熱性もあるので、夏はさらっと冬はあたたかい空間を演出してくれます。
ところが、そんな無垢材にもカビが生えてしまうことがあります。
いったいどんな場合なのでしょうか?
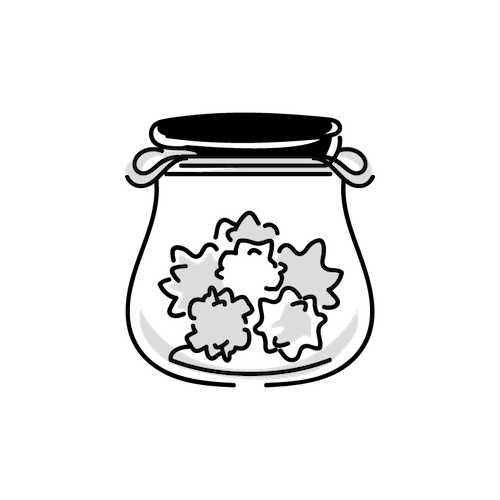
無垢材にカビが生えるのはいつ?
カビが発生しにくい無垢材ですが、それでもカビが生えてしまうのは、カビにとっての好条件が揃ってしまったとき!一般的に、カビが繁殖するのは「温度」「湿度」「有機物(栄養)」「時間」」4つの要素が揃ったときと言われています。温度は20〜30℃、湿度70%以上、栄養となるのは食べこぼしや髪の毛、フケなど、時間は経過時間が長ければ長いほど、カビにとって好条件となります。
つまり、特にカビが発生しやすいのは、気温と湿度が高い梅雨時期から夏にかけて、食べこぼしや髪の毛、フケなどがカビの栄養分となり、時間の経過とともにカビが繁殖しやすくなっていきます。もうお分かりですね?この条件が揃った時は無垢材に限らず、カビが発生しやすいということです。
無垢材を使った無垢フローリングの中でも、特にカビが発生しやすいのは、敷きっぱなしの敷布団の下、お風呂場近く、押し入れやソファの下、植木鉢周辺など。常に湿っぽく、換気や掃除が行き届きにくいところは、注意が必要です。
無垢材にカビが生えた時の対処方法
無垢材のカビが奥まで根を伸ばしてしまった場合、残念ながら完全に除去することはできません。そこで重要なのは、カビが発生したら奥まで根を伸ばす前に、なるべく早く対処してカビを取り除くことです!それでは、実際に無垢材にカビが生えてしまった時の具体的な対処方法を2つご紹介します!
エタノールでカビを取り除く方法
無垢材のカビはエタノールを使って取り除くことができます。
【準備するもの】
・マスク
・手袋
・消毒用エタノール
※スプレー容器に消毒用エタノール80mlと水20mlを混ぜたもの
・ぞうきん
・つまようじ
①まず、窓を開けるなどして換気を十分にしてから、マスクと手袋をします。
②次に、エタノール水を含ませ、硬く絞った雑巾でカビ以外の部分で試し拭きをします。
無垢材の変色や脱色がないことが確認できたら、カビ部分を丁寧に拭き取ります。
汚れが残りやすいフローリングの溝は、つまようじでかきだします。
※拭き取り箇所は他の場所と若干色が変わることがありますが、たいてい乾いたらほぼ同じ色に戻ります。
③無垢材が完全に乾くまでは換気をしましょう。
頑固なカビの処理方法
頑固なカビの場合、エタノールを使ってもどうしてもカビが取り除けない場合があります。表面が植物オイル仕上げの場合は以下の方法を試してみてください。
①まず、カビが発生している部分を他の部分と区別するためにテープで囲います。
②次に、カビ部分をサンディングペーパーで削ります
③カビが除去できたら、塗布してあった塗料と同じものを塗って完成です。
※ウレタン塗装など植物オイル仕上げではない場合、コーティングのハゲや変色、脱色の恐れがあるのでこちらの方法は使わないでください。
カビ発生から時間が経過している場合やカビの根が奥まで伸びてしまっている場合など、どうしてもカビが取れない場合は専門家に相談しましょう!

無垢材にカビを生やさないための予防策は?
無垢材にも環境やお手入れ方法によってはカビが発生してしまうことがわかりました。
カビが生えてしまったら早めに対処するとしても、できることならば、なるべくカビが生えないように予防しておきたいものですよね。
実は、カビの繁殖要因である4要素(温度、湿度、栄養、時間)のうち1つでも欠けていたら、カビは繁殖しないんです!つまり、「温度を下げる」「湿度を下げる」「栄養をなくす」「時間の経過を避ける」を中心に考えてみましょう。意外と簡単そうじゃないですか?
では、このポイントを意識して、無垢材にカビを生やさないための予防策について見てみましょう。
こまめに換気する
カビの繁殖要因である「湿度」と「時間」を抑えるために、こまめに換気をしましょう。湿度が高い状態が続かないように心がけることが大切です。
天気の良い日はなるべく窓を開け放ち、空気を循環させます。
敷物やソファの下にも換気が行き届くようにするとより効果的です。窓を開けるタイミングで敷布団やラグも一緒に干したり、ソファの場所を移動させるなどして湿度が高くなりがちな無垢材をしっかり乾燥させられるようにしましょう。
こまめに掃除する
カビは、人のフケや髪の毛、食べ残しなどを「栄養」として繁殖していきます。また、これらをそのままにしておくと無垢材にふけや髪の毛がこびりついて取り除けなくなります。完璧に排除することはなかなか難しいですが、こまめに掃除機や乾拭きをすることで、カビ発生の要因の1つである「栄養」を減らし、カビの繁殖を抑えることができます。電動お掃除ロボットをこまめに稼働させると効率よく「栄養」を取り除いてくれますよ!
「こまめな」お手入れをする
上記にあるように「こまめな」換気や掃除がカビ予防に効果的です。
「こまめに」お手入れをするとカビ発生要因の1つである「時間」の要素を除くことができますよね。「そのまま」「置きっぱなし」「敷きっぱなし」の状態を作らないことが重要となります。
無垢フローリングとうまく快適に暮らしていくには「こまめな」お手入れをしていくことが大切です。
こまめなお掃除方法はこちらをチェック!
無垢材のへこみの補修方法をご紹介!すぐにへこみ傷を修復しよう!
カビが発生しやすい場所を作らないようにする
そもそも、カビが発生しやすい場所を作らないようにするのもカビ予防の1つ。
具体的には下記の方法があります。
布団をフローリングに直接置かないようにする
人間は、寝ている間に大量の汗をかきます。布団にその大量の汗が吸収されて、それが無垢材の上に直接敷かれていると、これが「湿度」が上がる要因となるわけです。
布団の下にはすのこを置くなどして、無垢フローリングと布団の間に空気の循環を作ると、カビの発生を防ぐことができます。
また、布団もこまめに天日干しにして、乾燥させるのも効果的です。
お風呂場や押し入れなどに無垢材を使用しない
お風呂場などの水回りや押し入れなど、どうしても換気が行き届きにくく、常に湿度が高い状態になりやすい場所には、無垢材の使用をおすすめしません。家の設計やリフォーム計画をする際には、換気が行き届きやすい構造かどうかを判断して、使用する素材も変えるようにしましょう。
壁や天井にも調湿作用のある素材を使用する
無垢材には調湿作用がありますが、フローリングだけでは不十分です。壁や天井にも調湿作用のある珪藻土などを使用すると室内の調湿効果が上がります。室内の湿度が調整されていれば、常に湿度が高く保たれることがなくなり、カビが発生しづらくなるというわけです。冬場の乾燥も緩和されますし、エアコンなどの使用頻度も下がるので省エネや節約にもつながるので一石二鳥ですね!
家具は壁から少し離して配置する
家具を壁や床にピッタリとくっつけてしまうと風通しが悪くなり、カビが発生しやすくなってしまいます。家具はこまめに動かすのも大変ですよね。高湿度の状態が続かないように、家具はなるべく壁から10cmほど離して配置するようにし、ソファの下などはこまめに掃除や換気をするようにしましょう。

こまめなお手入れで無垢材と快適に暮らそう
いかがでしたか?換気や掃除、ていねいな暮らしで無垢材の醸し出す木のぬくもりとともに快適に暮らしていきたいものですね!
今回はここまで!次回もお楽しみに〜!
Category カテゴリー
その他の無垢材
-
無垢材
無垢材とは?集成材との違いとそれぞれのメリットについて
- 特徴
- 色・デザイン
-
無垢材
無垢材ってなに?無垢材の特徴とメリットデメリットをご紹介!
- 特徴
- 傷
- 色・デザイン
-
無垢材
無垢材のへこみの補修方法をご紹介!すぐにへこみ傷を修復しよう!
- 傷
- 手入れ
- 補修
1分簡単入力で
